はじめに
さて、2019年度分の課題請求締め切りも過ぎたことですし、2018年度のSecHack365に参加した記録をつらつらと書いていきたいと思います。割ととりとめもない感じになると思いますが、お付き合いいただければと。なお、起こったことを自分の視点からありのまま書いています。中には良いことも、悪いこともあります。正直な感想をそのまま掲載していますので、ご了承いただければと思います。
応募のきっかけ
2017年度からSecHackが始まったことは知っていましたが、あんまり自信がなくて見送っていました。そんな中ラボの後輩が参加しているのをTwitterで眺めたり、ラボで話を聞いたりして、来年は応募しようかなと言う気分になったりしていました。何やら1年かけてグループ開発で色々あったけれども賞を取ったとか、アメリカに行ったとかいう話も聞いてましたので、自分も何か「1年取り組んでみるもの」があっても良いかなと思ったりしたのが応募のきっかけです。
それで応募が開始されたわけですが、前年度とは違って3コースに分かれていました。とりあえず課題を見比べてみて、取り組めそうなものに応募してみようと思って選んだのが「思索駆動コース」でした。確か「一生かけて取り組んでみたいセキュリティな話題」という感じの、かなりざっくりした課題だったと記憶しています。それをA4一枚に収めて書いてきて応募してくださいという感じでした。当時の自分は何を思ったのか「北海道における冬期の灯油盗難事件が多発してるよねー」みたいな話を書いていました。このときは自分がどんなものについて取り組むのか全く思い描けてませんでしたし、今思い返すとよくこれで選考を通りましたねという感想を抱かざるを得ないところが…
それはさておき提出から数日経って、事務局のおなじみA氏から電話があって、SecHack365のトレーニーとして選ばれたことを知りました。実はこのとき初回の神奈川会と自分が主催するイベント(LOCAL Developper Day)が被っていて、神奈川回には遅れていくかもしれないという感じだったのですが、うまいこと後輩に業務を引き継いで最初から参加できるように調節することができました。あのときはありがとうございました!
神奈川会
ここでは初顔合わせでした。中には何度か顔を合わせたことがあった人もいたりして、全く知らない人ばかりじゃないという安心感が少しありました。また、そうした人からまた知り合いを紹介してもらったりしてその後仲良くなった人もいたり、割と思い出深い会でした。
初日は園田さんから習慣化をしていこうという話があったり、各トレーナーの自己紹介があったりしました。また、NICTは「えぬあいしーてぃー」と読むということをたたき込まれました。
2日目は一人ずつ持ち寄ったアイディアを30秒で話すピッチを行いました。前の人が発表したアイディアにどんどん自分のアイディアをかぶせていってわいわいしました。その後一人ずつ画用紙にアイディアを書いて、それを見せ合いながら説明する的なことをやった記憶だけ残っています。肝心の自分が何を話したかについてはほとんど覚えてないですね。何せ1年ぐらい前の話なので。
そしてコースに分かれていよいよコースワークです。柏崎先生率いる思索駆動コースは自己紹介をまず初めに実施しました。事前にスライドを作ってきてねと言われていたのですが、当日はなんとそのスライドを見せずに、ホワイトボードを使って説明しながら自己紹介をせよという無茶ぶりが行われました。初っぱなから飛ばしてくるのが思索駆動コースです(あれ、もしこれを今年もやるのだとしたら壮大なネタバレになってしまうのでは)。
それが終われば次は「思索大風呂敷」です。自分の漠然とした野望をとりあえず語って、それについて思索コースのメンバーから集中的に質問を受けて無駄な部分をそぎ落としていって、最終的に何か核になるものを見つけようという試みです。ここでも何を話したのかあんまり覚えていないのですが、おそらく「地方で何か役に立つことをしたい」みたいなことを言っていたと思います。結局最後まで「地方 x IT」という主張はずっと続けていくことになるのですが、このときは全然そんなことは考えてもいませんでした。
神奈川会のあまり真面目ではないツイートをいくつか貼っておきます。SecHackでは毎回おやつコーナーが用意されて、大量のおやつと飲み物(特にドクペタワー)が提供されるのですが、その内容については参加者から結構いろんな意見が飛び交っていたりします。欲しいおやつがあったらA氏に相談じゃ!
北海道会
近くて遠い北海道回です。道内から移動といえども、軽く2時間ぐらいはかかります。大通付近で集合というかなり恵まれた集合場所だったんですけどね。
そしてそのままさくらインターネットの石狩データセンターに向かいました。小規模なデータセンターは見たことがあったのですが、ここまで大規模なものは初めてだったのでかなり楽しみにしていきました。道民のIT界隈ではおなじみの"母"も会場で色々とお世話してくれました。データセンター内の出来事についてはあまり詳しく書けないのですが、機器の保護のために靴カバーを履いて各種サーバー群を見てきました。圧巻でしたねー。これもぼかしますが、様々な点において試行錯誤の痕跡が見られて、こんな風に運用していくんだという知見が溜まりました。データセンター見学、オススメです。
さて、ここでここで賛否両論を巻き起こし、大問題となった2日目について語らないわけにはいかないでしょう。何がそんなに問題になったのかというと「くぼたつ道場」でのできごとです。「アイディアを発想するための方法」を身につけるというのがこの道場の目的だったのですが、内容の説明が「〜を書け」とか「〜しろ」とか完全に命令口調で、少なくない人が萎縮してしまってアイディアを発想するどころか何も考えられない状態に陥ってしまいました。僕もその一人です。もちろん、ここで行われた内容については特に何も感じなかった人や、楽しかったという人もいましたが、僕はそういうタイプではなかったのでただ縮こまって思ったことをハッシュタグを付けずにTwitterに放流しながら時が過ぎるのを待つしかありませんでした。でも、ここで共感してくれた人にはとても感謝しています。ありがとうございます。そうでなければこの出来事は乗り越えられなかったと思うので。
嵐が過ぎ去った後は習慣化についてのセッションでした。ここは平和でしたね。習慣化するハードルを下げようとか、そういうお話しがメインだったと思います。あとはマンダラートなどなどのお話しですかね。でもぶっちゃけるとこの後マンダラートはあまりやらなくなっちゃいました。佳山さんごめんなさい…
お次はコースワークの「思索袋小路」です。これはオンラインゼミに参加できなかった人に、まるでその回にいたかのような状態になってもらうことを目的として行われました。思索駆動コースでは毎週オンラインゼミを開催していて「自動運転」や「漫画村」などといったテーマについてそれぞれまとめて「他の人が話題にしなかったこと」について語るということをやっていました。これも都合があって参加できない日が発生するため、その人のキャッチアップをしようという感じです。
続いてお楽しみの縁日です。僕は川合さんの「90分で作る自作言語入門」とy-tel先生の「RaspberryPiで作る自作ルーター」の2コマに参加しました。自作言語の方は簡単な言語でしたが、変数とか足し算とか実装できて面白かったです。途中でtime関数がセグフォしたりして大変でしたが。RaspberryPiのルーターは前の人の設定が残っているのに気づかなくて「あれ、繋がらない」などと時間を溶かしてしまい、結局最後まで完成させることができませんでした。くやしー!
最後に柏崎先生からコース全体に向けてライブコーディングなどをしつつお別れとなりました(※僕はVim派です)。
福岡会
福岡会です。人生初の福岡です。前泊だったのを良いことに、OBとして参加していたラボの後輩と一緒に、福岡会が始まる前に博多の屋台を楽しんできました。屋台でビールをあおりつつ、焼きラーメンとか、明太子入りだし巻き卵とかに舌鼓を打っていました(これ夜中に書いてるんですけど、思い出したらセルフ飯テロになってました)。さらにお昼集合だったのを良いことに、朝早くに西鉄に乗って太宰府天満宮まで行って、無事に修了できることをお祈りしてきました。振り返ってみるとこれが後々効いてきたのかと思ったり思わなかったり。
さて、福岡会最初はヌーラボ社員の皆さんとの交流会でした。なんと社長さんが忙しいスケジュールの合間を縫ってお話ししてくださったり、色々と面白かったです。また、OBの方々もここで自己紹介をして「どんどん頼ってください!」的な空気感になっていました。
終わってからは会場の志賀島へ移動です。九州と志賀島は砂州で繋がっているのですが、その真ん中にぽつんと道路が敷設してあってなかなかに珍しい光景でした。また、ホテルまでの道はかなり狭い道路だったのですが、あの大型バスで良くこんなところを運転していくなぁとただただ感心したことはよく覚えています。ここのホテルは無限イカ刺しが名物のようで、皆さんこぞって食べてました。
2日目は習慣化の話があってから、いよいよ中間発表です。全員が全員にコメントする仕組みになっていて、聞いている方も油断できない状況です。この日のために中間発表用のネタはもちろん用意してきていました。苦し紛れに出したアイディアだったのですが、振り返ってみるとこの頃にはもう最終発表のネタ、つまり「マイナンバーカードで認証機構を作ってみよう」という主張を始めていた模様です。短い発表でしたが、ありがたいことにトレーナー賞をいただきまして、DEFCONのTシャツをもらいました。実はまだ一回も着てません。神戸で一人暮らしを始めたら会社に着ていきたいと思います。それはそれとして、この後チームを組んだあたりから迷走を始めるんですけどね。振り返るとそれもまた必要な経験だったのかもしれないですけど。
で、終わったら海です、海。めっちゃ青くて透明な海です。普段は冷たくて荒々しい太平洋しか見たことがなかったのでそれはもう感動的でした。海ってこんなに暖かかったんですね。でも僕は海遊びはほとんどせずにゴミ拾いの方をお手伝いしていました。焼けたテントとか落ちてて一体何をした飛んだという気分になったりも。
最後に倫理セッションを行って終了。検事経験のある方から直接法律的なお話を伺える貴重な機会でした。
そして後泊だったのを良いことに、博多駅地下にある一蘭に行って豚骨ラーメンを食べてきました。やーおいしかったです。味集中スペースの試みも面白いですよね。せっかくだからと替え玉も体験しちゃいました。
山形会
山形会は会場にたどり着くまでがすさまじかったです。仙台空港に降り立った後、仙山線経由で山形まで向かったのですが、これがひたすらに山の中を走るだけの路線で、よく言えば自然が豊か、もうちょっと踏み込むと人工物が線路以外何もない、そんな列車旅でした。
そしてこちらも前泊だったのを良いことに山形城跡や旧山形県庁舎などを見学してきました。山形城は復元を目指しているようなのですが、どうも資料が足りないようで集めるのに必死な感じを醸し出していました。旧山形県庁舎は北海道でいう赤レンガ庁舎(旧道庁)に似ている感じでした。やっぱりこういう建物が残っているのは良いですね。

山形城跡

旧山形県庁舎
山形会のメインは中間ポスター発表です。これが振り返ってみるとあまりできの良いポスターじゃなかったなぁと。福岡会が終わった後は先ほども言ったとおりチームを組んだのですが、どこかひとつの領域について深く考察していくのではなく「いろんな可能性」について検討しすぎたせいでどっちつかずの内容になってしまったんだと思います。でもコースマスター的には「悩め〜悩め〜」という感じだったので、遠慮無く悩むことにしました。
ちなみにこのときはどの辺まで迷走していたかというと、マイナンバーカードだけじゃなくて任意のNFCデバイスで認証できるようにしたら良いんじゃないかとか、そもそも認証だけじゃなくてもうちょっと広い感じの利用ができないかとか、そんなことばっかり考えてました。実は「任意のNFCデバイス〜」と言い出したのは原因があって、このときはマイナンバーカードの仕様が全くわかっていなかったため、その他のNFCデバイスでも認証できるように保険をかけておこうという意図が働いたせいだったりします。
ポスター発表が終わったらリフレッシュもかねて山登りです。会場は蔵王だったのでちょうど紅葉の季節でした。走って登ってきた方もいましたが、大半の皆さんはロープウェーで山頂まで行き、さらに沼まで歩いて行きました。以下、沼の様子です。
そしてお楽しみの基調講演はアメリカで行われているCanSatの紹介です。アメリカの広大な砂漠で、惑星探査機を模したシステムを作ってミッションをクリアしていくというコンテストなのですが、これがなかなかに過酷なレースのようで思わず見入ってしまいました。どうも砂漠で迷うと大変なことになるらしく、文字通りサバイバルすることになるんだとかなんとか…
その後はハロウィンパーティーと称して仮装をして妙にノリノリのトレーナー陣と一緒にケーキを食べる会が催されました。こういう楽しいリフレッシュ企画があるのもSecHackの良いところだと思います。あとこれはここだけの秘密なのですが、2つ目のケーキおいしかったです。
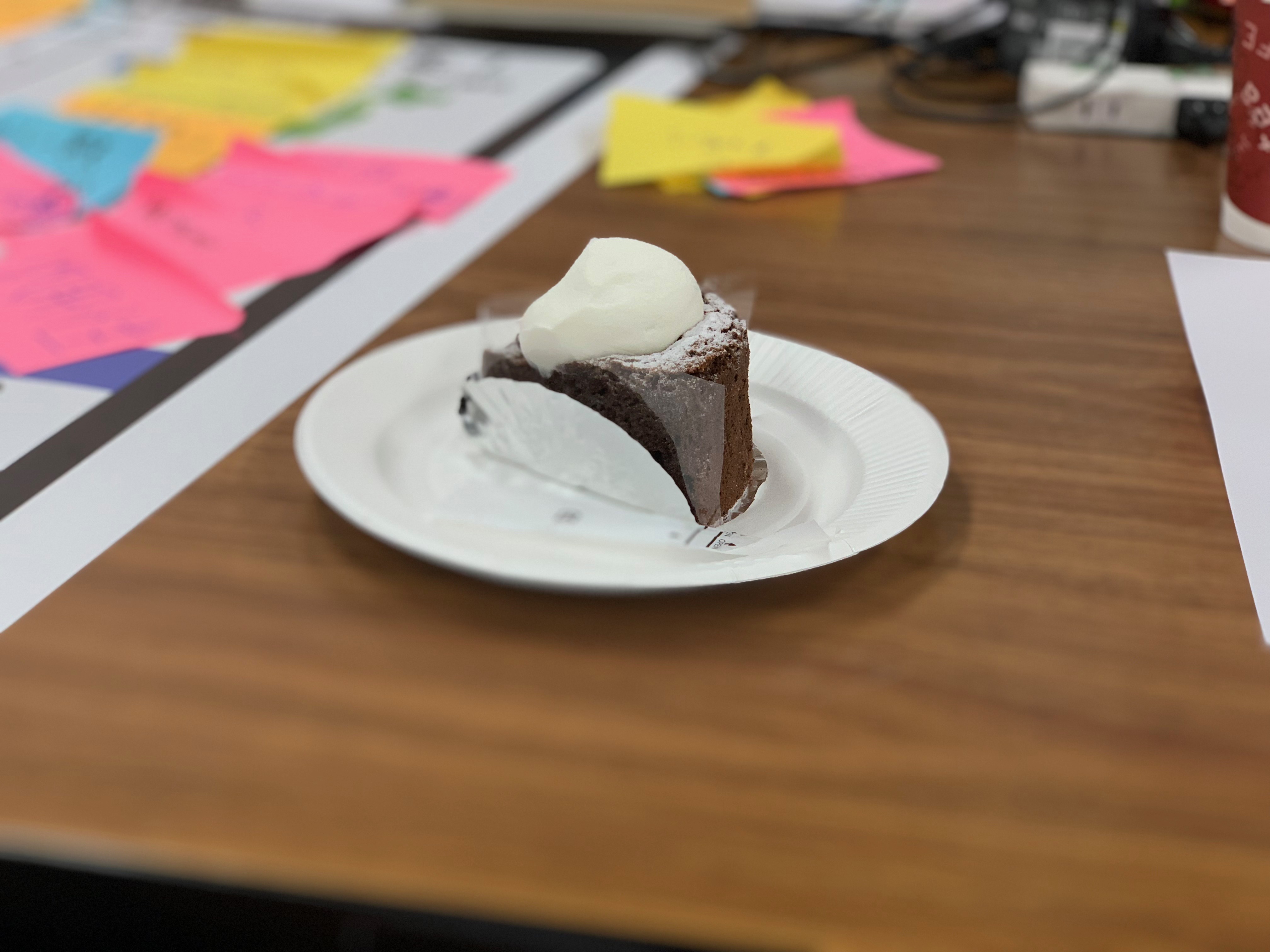
ケーキ(1)
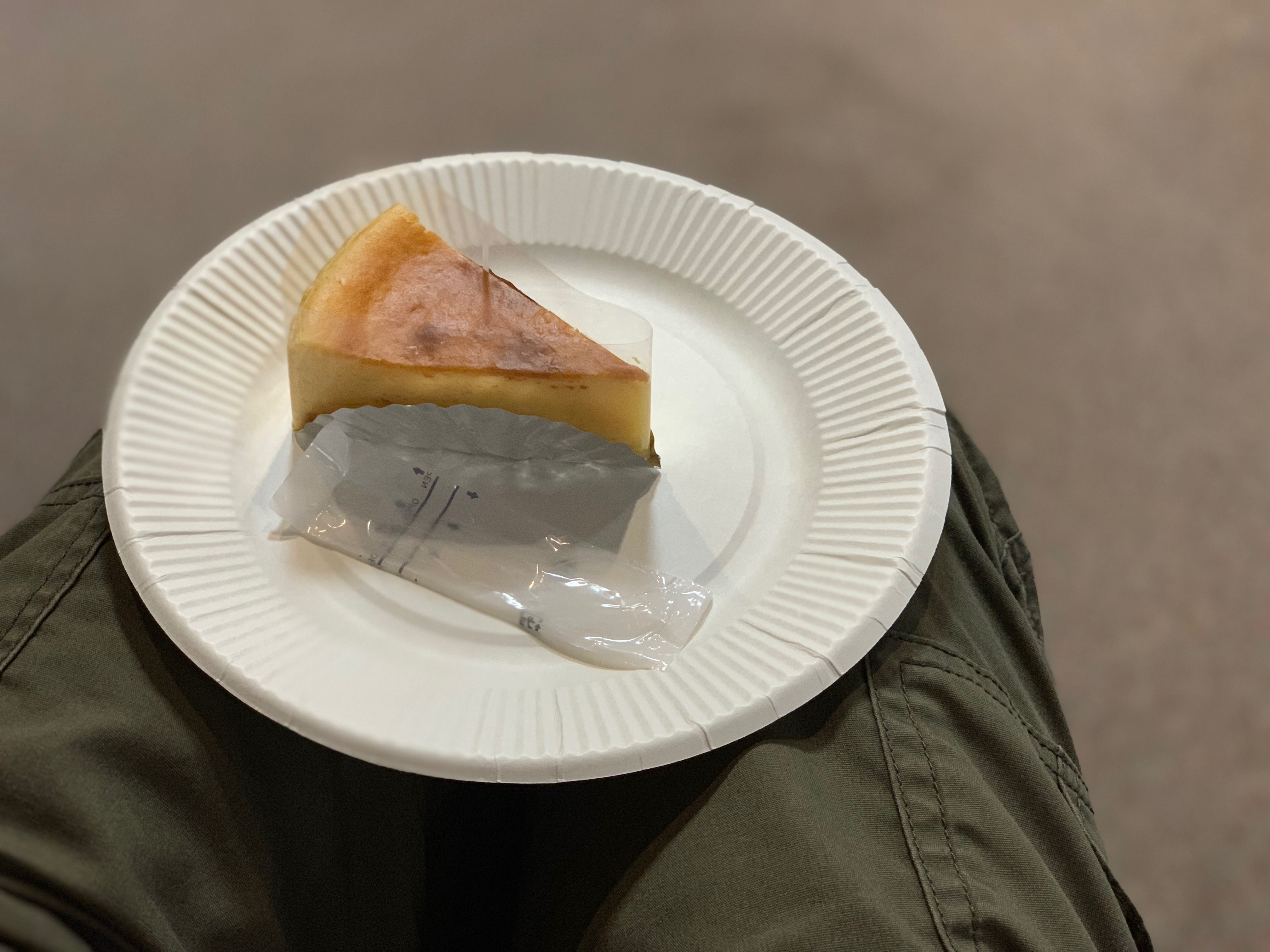
ケーキ(2)
愛媛会
人生初の四国でした。一応先祖は四国の出身らしいので、5世代ぐらいぶりに故郷の土を踏んだことになります。そんな感慨深さもありつつ、今回も例によって前泊なのでせっかくだからと伊予鉄に乗って道後温泉本館に行ってきました。調子に乗って高い方のお風呂にも入ってきたのですが、これが他のお客さんが一切いなくて完全に貸切状態で、大変あずましく過ごすことができました。ラッキー。ただこのあと大変な事態に巻き込まれるんですけどね。館内は撮影禁止なので、外の様子だけ。

道後温泉本館
次の日の午前中も時間があったので、松山城に行ってきました。北海道には松前城以外の日本式のお城が存在しないので、これが初体験です。その大きさや広さに圧倒されつつ、階段がめっちゃ急で怖い思いをしたりとか、なかなかに刺激的な体験でした。しかし私はロープウェーを降りたところではたと気づいてしまったのです。チームメイトが作ると宣言していたスライドが未だ完成していなかったことに。仕方ないのでロープウェーの駅で「えひめFree Wi-Fi」の電波を拾いながらなんとかスライドを書き上げました。この出来事は後々の行動に繋がっていくことになります。

松山城
そして会場到着。奥道後温泉というところでした。が、なぜか隅々にまで貼られている「SecHack3"5"6」の案内看板。最初の1枚だけは合ってるのにどうして…
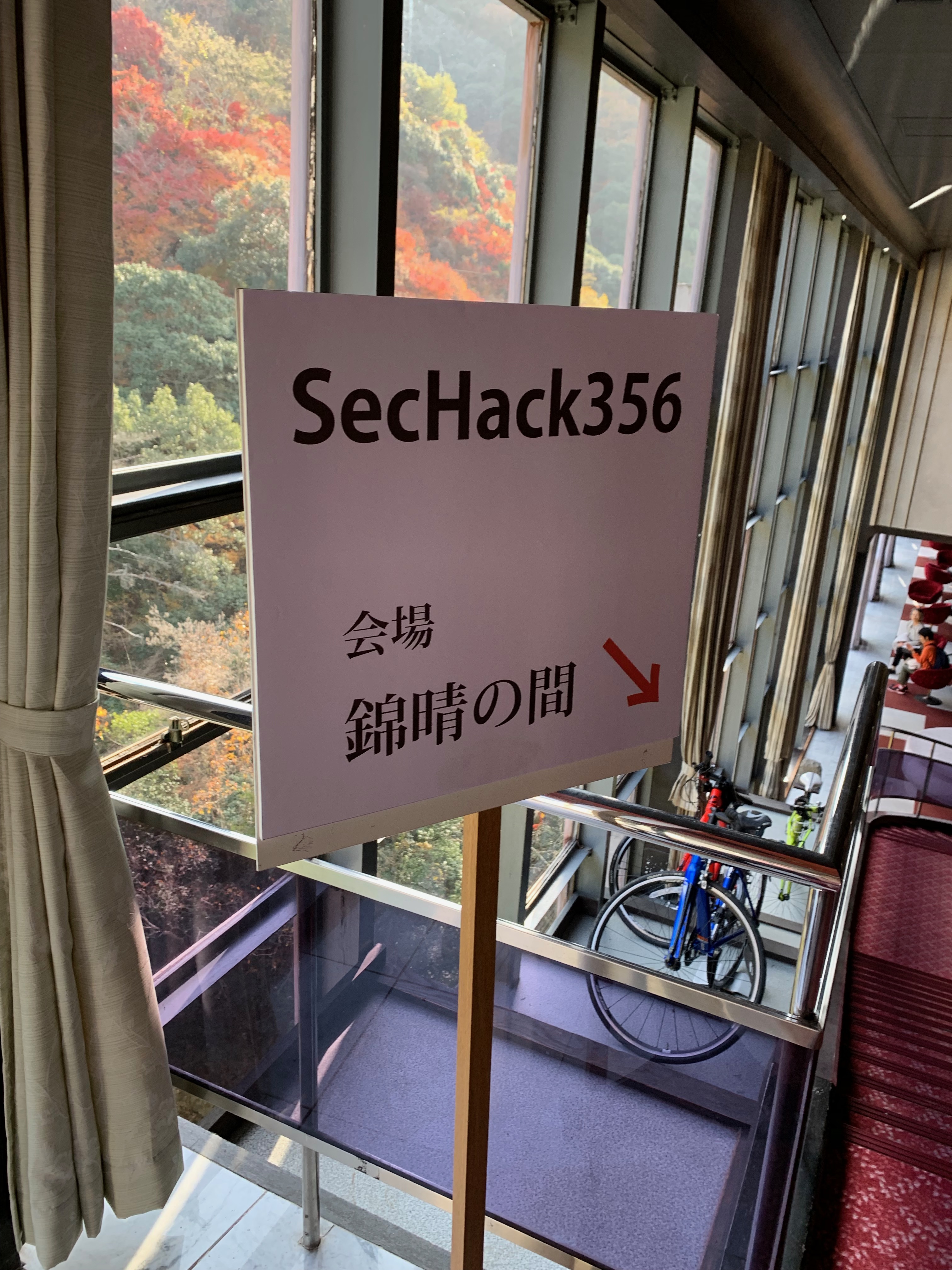
SecHack356
いよいよプレゼン発表ということで、先ほど慌てて作ったスライドで発表しました。でもこのとき前回と内容があまり変わっていなかったんですよね。とりえあず前回突っ込まれていたポイントとかはかわせるように修正してありましたが、それでもやっぱり振り返ってみるとピンボケした感じの発表だったなぁと今でも思います。
そしてここからは基調講演その1。まずは米空軍の方から貴重なお話が聞けました。自衛隊のレベルは全く低くないけど、絶対数が足りなすぎるというお話しがとりわけ印象的でした。うーむ、ここを増やして行くにはどうしたら良いんでしょうね。これでまたひとつ思索ネタできそうですね。
2日目。ポスターとデモの発表です。Nuxt.jsとWebUSBを使って急ごしらえでFeliCaを使った認証ができるものを用意して臨みました。ちなみにこの時点でも全くマイナンバーカードの仕様について明らかになる見込みは立っていませんでした。そういうわけでFeliCa認証でお茶を濁していたわけですね。この頃は漠然とFeliCaでなんとかするしかないかなぁなんてちょっと弱気になったりもしてました。
そんなこんなで発表が終わって、リフレッシュのお散歩です。ここでもきれいな紅葉が見れて良い気分転換になったと思います。若干お散歩タイムが短かったような気もしますが…

葵のご紋が彫られた灯籠

紅葉
修了生LTが終わった後、基調講演その2が行われました。あえて地方でITのお仕事をしているという高知AIラボの興梠さんがいらっしゃると聞いて、このお話を愛媛会の中で最も楽しみにしていました。神奈川会の頃からずっと「地方xIT」と主張し続けていましたからね。元々は東京にいたとのことでしたが、いろいろな都合で高知からしか働けない人に合わせてみたらなぜか人数が増えて今の体制になったとのこと。どうやって東京との連絡を取り合っているのかとか、持続している秘密が知りたくて詳しい話を聞きたくなってきたところで、トレーナーの方が気を利かせてわざわざ引き合わせていただけました。なんとありがたい。
しかしここで大事件が発生するわけです。別の人が会話に割って入って来てしまってですね、私が聞きたかった事が全く聞けないまま会場閉鎖の時間になってしまったわけです。しかもその内容が別に興梠さんに聞かなくても良いような内容で、聞いているこっちが辛くなってきちゃいまして、その後ずっと不機嫌な感じで過ごしてしまいました。まぁ、その次の落語はゲラゲラ笑いながら見てたんですけどね。
あ、あと最後にひとつ。歯ブラシ返してください。

空港の蛇口からミカンジュースが出るやつ
愛媛と沖縄の間
ここでかなりの進捗があったのでここだけは触れておきたいと思います。逆に言うとここに来るまで大して進捗していなかったということになるのですが…
どういうことか愛媛会が終わった後、目指す方向性の違いからチームは解散していて、ソロでの参戦となってしまいました。チームを作った人は多かったのですが、チームを解散したというのは自分らのところだけだったかと思います。この時期にチーム解散しても全然なんとかなりますが、それなりの覚悟は求められるのでそこだけは注意してください。合わないと思ったら無理にチームを続ける必要も無いんだなぁという学びでした。
ここで何か吹っ切れたのか、マイナンバーカードのリバースエンジニアリングに取り組み始めました。これがちょうどお正月頃だったと思います。修論発表も迫っていたのですが、こっちが先と割り切って黙々と作業してました。その後かなり胃を痛めながら修論にも取り組んだんですけどね。リバースエンジニアリングの手法としては、WireSharkで流れるパケットを見たり、既存の実装を参考にしながらJavaScriptでWebUSB用のパケットをバイナリから組み立てていく地道な作業を延々と繰り返していました。
詳細は省きますが、最終的にはマイナンバーカードから公開鍵を取り出すことと、秘密鍵を使って任意のバイナリ列にサインすることができるようになったので、認証システムの構築にも取り組みました。この辺はパスワードレスにしたかったのでWebAuthnのプロトコルも参考にしつつDjangoを使って組み上げていきました。本当はWebAuthnに乗せるところまでやってみたかったのですが、WebAuthnの「認証機」を作るためにどのような仕様を満たせばいいのかがさっぱりわからなかったので若干妥協しました。
システムができても安心していられません。15分喋るスライドを用意せねばならないのです。今回はソロ参戦ですから、分担したりとか誰にも頼れないわけですね。技術に明るい人を相手に話すことを念頭に、どういった技術を使ってこのシステムを構築したかとか、リバースエンジニアリングにはどのような手法を使ったかとか、そういう視点からスライドを組んでいきました。もちろん、これを作った動機も忘れてはいけません。「地方xIT」なんだということをしっかりとアピールしていきました。
沖縄会
そういうことで迎えた沖縄会。3日間ある日程、全部発表です。しかも沖縄会終了2日後には修論発表会が迫ってます。でもその前に、例によって例のごとく前泊なのを良いことにソーキそばを食べてから首里城まで行ってきました。ずいぶんとお気楽ですね。ゆいレールの終点、首里駅まで乗っていくわけなのですが、途中すごい勾配のところがあったりして「こりゃモノレールじゃなきゃ登れないなぁ」などと考えていました。建物の感じとかも北海道とは全然違ったので車窓も飽きませんでしたね。首里駅では今年の夏に開業予定の延伸部分がすでにできあがっていて、いよいよという感じを醸し出していました。
首里城までは首里駅から徒歩15分ぐらいのところにあります。結構道ばたにアップダウンがあるので、歩いて行くとちょっと疲れるかも。あと2月なのにとてつもなく暑いのでそこも要注意です。平気で20度以上になります。首里城自体は2000年に復元されたものなので、割と新しい感じ。でもきちんと再現されているので見応えはたっぷりです。

おなじみ「めんそーれ」看板

ソーキそばのソーキは上に乗っている豚肉のことなんだとか

モノレールの延伸部分。2019年の夏以降に開業らしい

首里城の門
そして集合場所である空港で他のトレーニーを待っていたら竹迫さんから「ルートビア飲んだことある?」と聞かれたので「ないですねー」と応えたら一口くれました。湿布の味でした。会場に着いたらルートビアのタワーができてて卒倒しそうになりましたけど。

ルートビアタワー
いよいよ発表ですね。この発表の中から秋葉原会で発表する人が選ばれることになります。FeliCaやマイナンバーカードで認証するデモを見せつつ、作ってきたスライドを発表しました。人によるのかもしれませんが、自分の場合はリアクションを取ってくれる人の方を見ながらやると話しやすかったです。もし発表のコツについて悩んでいる人がいたら参考にしてみてください。実はこのスライド、結構なブラックジョークが混ぜてあったのですが、これがフラグになるとは全く思ってもいませんでした。他の人の発表も聞きつつ、感想も入れつつ、結構集中していました。ツイートも少なかったみたいですし。
一晩明けて朝ご飯を食べたらいよいよ結果発表。なぜかスターウォーズ風に紹介されました。誰の趣味だったんでしょうね。で、自分の作品名が流れてきてびっくりですよ。びっくり。ほんとに1年間紆余曲折あったけど頑張ってきて良かったなと思えた瞬間でした。それは同時に秋葉原会でのスライドを作らねばならないということにも繋がっていくんですけれども…
発表が終わったら基調講演、沖縄オープンラボラトリの山崎さんのお話しです。山崎さんのお話は結構毒のある感じでして、Typetalkで議論が盛り上がっていました。自分的な結論としては、以下のツイートに集約されています。想定している聴衆は、我々の先にいたんですね。たぶん。
クロージングを終えた後はリフレッシュということで知念岬と斎場御嶽(せーふぁうたき)に向かっていきます。琉球方言は「え→い」「う→お」に母音が置き換わる特徴があるらしく、こんな読み方になるそうです。難しいですね。知念岬でまずサーターアンダギーをごちそうになって、それから岬の先端で記念撮影をしました。一部下に降りていった人がいて写ってない人もいましたけど…

ニライカナイ橋。「ナイ」で終わると北海道っぽい

知念岬でサーターアンダギーをおごってもらいました

知念岬から見えるビーチ
それから徒歩で斎場御嶽に向かっていきます。かなり上りますし、暑いです。2月ですが、水分必須ですし、日焼けもするので対策が必要だと思います。北海道に戻るとダウン着ないとやってられないぐらい寒いんですけどね。斎場御嶽は男子禁制だったようで、琉球王ですら女装しないと入れなかったと入口に書いてありました。いまでも地元の人がお祈りに来る生きた聖地なので、そういったことを邪魔しないように密かに眺めるのがお作法のようです。

聖水の壺

祈りの場所

入口を示す灯籠

身を清める井戸にはイモリがたくさん
沖縄から秋葉原の間
沖縄会も終わって、修論を無事に仕上げた後、秋葉原会で使うポスターとスライドを用意し始めました。秋葉原会では一般の人が来場するため、沖縄会で作った技術に明るい人向けの説明はちょっと不適切かなと考えて、大幅に作り直すことにしました。それで内容を整理しつつ、ちょっとブラックなジョークを交えながら「マイナンバーカード」を軸に据えてみようと色々試行錯誤していました。それでいったんタイトルを「マイナンバーカードをハックしてみた」という感じにして提出したのですが、その後こんなツイートをすることになるわけですね。
ここで何があったかというとですね、y-tel先生からtelがかかってきまして「ちょっとタイトルが過激なので修正してもらえないか」というお話しがあったんですよ。ここで佳山さんから以前言われていた「どうせ言いたいことを伝えるならポジティブにやろう、毒を入れる必要は無いんだよ」という言葉を思い出しまして、修正に応じることにしました。この言葉がなかったらもっと最終発表が混沌としていたかと思うとありがたい限りです。それでポスターも急遽修正することになりまして、本番直前に慌ただしい日々を送ることになりました。
というわけで作戦変更をすることになり「CivicTech」を軸にしてプレゼンをしようと思い立ちました。20分という持ち時間の中でそうした背景を説明するために、思い切ってFeliCaでの認証はばっさりカットして「地方にもセキュアな認証」を提供するにはこのシステムが必要なんだというアピールを中心に据えることにしました。
秋葉原会
秋葉原会でプレゼンをする人は前日に集合してリハーサルを行います。到着した人から順次実施していくので、遠方の人が遅れていっても大丈夫なようになってました。ありがたいです。まず一通り発表して、トレーナー陣から集中砲火を浴びます。優秀者に選ばれたんだからこれぐらいはできるでしょ、という感じですね。内容だけでなくて発表中の手の置き方とかデモでのしゃべり方とかそういうところまでアドバイスしていただきました。ありがとうございます。ちなみに修論発表よりがっつり添削されました。あれ、おかしいな…
一晩明けて、ぎゅうぎゅうに詰め込まれた総武線各駅停車に乗って会場入りしました。やはり平日朝の総武線はヤバイ。接続チェックがあるので9時に来てと言われたのですが、結局時間を持て余すことに。会場では接続確認の他にポスターの掲示やデモの準備もしなければならなかったのですが、自分のポスターは上記の理由によって到着が遅れていたため、届くまで暇してました。なぜか梱包を解くのが面倒だからという理由でデモ用に新品のモニターがあてがわれましたが、アレは一体何だったのか。そして仕出しのお弁当を食べて、お客さんが入場してくるまで待機です。
13時になっていよいよスタート。開式の挨拶やらが終わってからネクストバッターボックスで待機です。発表順が2番目だったのでね。発表自体は何度も練習してますし、割とプレゼン慣れしているところはあるのであんまり緊張はしないのですが、待ってる間はなぜかドキドキしちゃいました。ちょっとデモの動作が不安定だったことと、Webセキュリティ界隈で大変有名な方がお見えになっていたことも要因ではあるのですが…
発表は無事に終えまして、次はブースに戻ってお客さんに説明していきます。結局10人ぐらいの方に説明したと思います。発表が終わって真っ先に「Webセキュリティ界隈で大変有名な方」がお見えになって、発表時よりよっぽど緊張しながら説明しましたが、成果物について大変興味を持っていただけたようでありがたかったです。最後になぜかツーショット写真まで撮らせてもらいました。他にも子供が今度参加したがっているという親御さんや、次回参加してみようと考えている学生さんなどいろいろな人とお話ができました。また、やたら技術に詳しいご老人とお話しして最初は誰だろうと疑問に思ったのですが、後でこっそり確認したらNICTの徳田理事長だったことが発覚してビックリしました。知らなくてごめんなさい…
そんなこんなで説明していたら衛藤室長の取り計らいで、ご来場いただいていた佐藤ゆかり総務副大臣に直接ポスターの説明ができることになりました。僕の発表は総務省に向けて規制緩和を働きかけるものでもあったので、大変ありがたい機会を頂戴しました。30秒で、といわれていたのですが、結局2分ぐらい話したと思います。後で「長い!」と怒られました。すみません。副大臣は「えぇ」としかおっしゃりませんでしたが、頭の片隅にでもインプットできればそれで大成功です。何かのきっかけに思い出していただければと思います。
そんなこんなでポスター発表も終わり、閉会式やピザや寿司が振る舞われる懇親会などを経て修了証書の授与式が行われました。修了証書の他に記念品としてSecHack365のロゴが入ったブランドもののボールペンと手帳をいただきました。こうして1年間かけたSecHack365は終了していきました。
おわりに
ざっくり1年間を振り返ってみました。SecHackの思索駆動コースを通じて一番強く意識できたのは自分が「地方 x IT」にもっと取り組んでいきたいと思えたことです。今までもなんとなくそういう行動は特に意識せずにしていたのですが、思索ゼミを通してきちんと言語化できるところまで持って来れたと思います。
言語化できた結果として、あまり利活用の進んでいないマイナンバーカードに注目して、実際に使えるものを提供することで「全国津々浦々でセキュアな生活が享受できるようになろう」というビジョンを示せたと思います。優秀者に選ばれても選ばれなくても、この思索駆動コースでの体験を通じて得た経験は、一生残るものになったと感じています。
そういった体験ができますので、チャレンジしてみたくなった人はぜひ気軽な気持ちで応募してみてください。卒論/修論と被っても多分なんとかなります。というかなんとかしました(生存バイアスの可能性が高いですが)。交通費は向こうが出してくれて、前泊・後泊の手配もしてくれるので、辺鄙な土地にいても参加できます。作りたいものが最初は明確になっていなくても、各オフライン会でのゼミを通じて思索を深めていった結果、全員が成果物を作りさらにその背景を説明できるまでになりました。応募前にはいろんな懸念があるでしょうが、それでも思い切って応募すれば、あとは意外となんとかなるというか、なんとかせざるを得なくなるので大丈夫です。飛び込んでみてください。
それでは長くなったのでこの辺で。来年度以降の皆さんの挑戦を応援しています。
P.S.
前泊なのを良いことに各地の観光地に行きまくっていましたが、色々と自己責任ですのでお気を付けください。観光地でけがして参加できなくなりました、とかになってくると悲しいので。